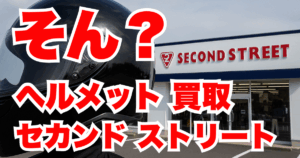ハンターカブ CT125のカスタムを考えているなら、マフラーガードの選択は欠かせないポイントだ。
純正のマフラーカバーは十分な保護性能を備えているが、より個性的なスタイルや耐久性を求めるなら、社外品への交換や黒塗装などのカスタムも検討したい。
特に、ヨシムラ製のマフラーガードはデザイン性と耐熱性に優れ、多くのライダーに支持されている。
また、CT125 ヒートガード 純正のままでは満足できない場合、より広範囲を保護できるカスタムガードやCT125用 CT110マフラーガード取付コンバーターブラケットキットを活用することで、適合しないパーツでもスムーズに装着できる。
さらに、純正ガードを黒に塗装することで、より引き締まった印象を与え、汚れや傷の目立ちにくさも向上する。
この記事では、ハンターカブ マフラーガードの選び方やカスタム方法、ヒートガードの外し方、さらにはCT125 マフラーガード 塗装の手順まで詳しく解説。
CT125 CC110マフラーガードの違いや、マフラー周りのパーツ選びのポイントも紹介しているので、自分に合ったカスタム方法を見つけ、愛車のスタイルをより一層引き立てよう。
- ハンターカブ マフラーガードの役割と、安全性・耐久性の向上について理解できる
- 純正マフラーガードと社外品の違いや、それぞれのメリット・デメリットを把握できる
- マフラーガードのカスタム方法(交換・塗装・取付キットの活用)を具体的に学べる
- ヒートガードの外し方や取り付け手順を知り、自分で作業できるようになる
ハンターカブのマフラーガードの魅力と選び方
- ハンターカブのマフラーガードとは?役割と必要性
- 純正マフラーガードと社外品の違い
- マフラーガードの材質と耐久性
- 黒塗装のマフラーガードのメリット
ハンターカブのマフラーガードとは?役割と必要性

ハンターカブのマフラーガードは、バイクの性能やデザインを損なわずに、ライダーの安全を確保しつつ、マフラーの耐久性を向上させるための重要なパーツだ。カスタムパーツとしても人気があり、多くのライダーが交換や追加を検討している。
マフラーガードの基本的な役割
マフラーガードの最大の役割は、ライダーや同乗者がマフラーに直接触れてしまうのを防ぐことだ。ハンターカブのマフラーは、エンジンの熱を排気する関係で非常に高温になる。特に長距離ツーリングや渋滞時など、エンジンの稼働時間が長くなると、その温度はさらに上がる。誤って触れると火傷を負う可能性があるため、ガードがあることで安全性を確保できる。
また、マフラーガードはバイクが転倒した際に、マフラー本体へのダメージを軽減する役割も果たす。特に、オフロード走行や林道ツーリングが多いハンターカブの場合、転倒のリスクは一般的なバイクよりも高い。ガードが衝撃を和らげることで、マフラーのへこみや傷を最小限に抑えることができる。
マフラーガードの必要性
ハンターカブのオーナーにとって、マフラーガードは必要不可欠なパーツといえる。純正のガードでも一定の保護機能はあるが、より頑丈なものやデザイン性に優れたものに交換することで、さらに安心感が増す。
- 安全性の向上
先述の通り、高温のマフラーに触れるリスクを軽減できる。特に、タンデム走行(2人乗り)の場合、後部座席の同乗者が足をマフラーに近づけてしまうケースが多いため、安全対策としてガードは欠かせない。 - マフラーの保護
転倒時のダメージを減らすだけでなく、飛び石や泥跳ねからマフラー表面を守る役割もある。オフロード走行を楽しむライダーにとって、ガードがあることで傷や錆びを防ぎ、長く美しい状態を維持できる。 - カスタムとしての魅力
マフラーガードには、さまざまなデザインのものが販売されている。ブラック塗装やクロムメッキ仕上げ、耐熱素材を使用したものなど、個性を出す要素としても活用できる。ハンターカブはカスタム志向の強いバイクのため、細部までこだわることで、より自分らしいスタイルを表現できる。
純正ガードと社外品の違い
ハンターカブには、最初から純正のマフラーガードが装備されているが、社外品と比較するとデザインや機能性に違いがある。
- 純正マフラーガード
純正品はメーカーが安全性を重視して設計しているため、適度な保護性能を備えている。ただし、デザインがシンプルで、個性的なカスタムを求めるライダーには物足りないかもしれない。 - 社外品のマフラーガード
カスタムメーカーからは、軽量かつ強度の高いマフラーガードが多く販売されている。たとえば、耐熱性に優れたカーボン製、無骨でタフな印象のスチール製、ブラックやシルバーで統一されたものなど、幅広い選択肢がある。デザインを重視するなら、社外品の導入を検討するのも良いだろう。
まとめ
ハンターカブのマフラーガードは、安全性を高めるだけでなく、マフラーの保護やカスタムの一環としても重要なパーツだ。特に、オフロード走行や長距離ツーリングを楽しむライダーにとっては、転倒時のダメージ軽減やマフラーの耐久性向上に役立つ。純正品と社外品の違いを理解し、自分のスタイルや用途に合ったマフラーガードを選ぶことで、より快適で安全なバイクライフを楽しめるだろう。
純正マフラーガードと社外品の違い

ハンターカブのマフラーガードには、大きく分けて純正品と社外品がある。それぞれに特徴があり、どちらを選ぶかによって、バイクのスタイルや性能、安全性に影響を与える。ここでは、純正と社外品の違いを詳しく解説し、自分に合った選択ができるようにしよう。
純正マフラーガードの特徴
ハンターカブ(CT125)には、メーカーが開発した純正のマフラーガードが標準装備されている。これは、安全性や耐久性を重視して設計されており、多くのライダーにとって安心できる選択肢だ。
- メーカー設計による安心感
純正マフラーガードは、ホンダが開発・設計したものであり、CT125のエンジンやマフラーの熱を効率的に遮断できるように作られている。そのため、長時間のツーリングや渋滞時でも、マフラーの熱から足やズボンをしっかり守る。 - 耐久性に優れた設計
純正品は、ハンターカブの使用環境を考慮し、オフロードや長距離走行に耐えられるよう設計されている。特に、衝撃に対する強度が考慮されており、転倒時のダメージを軽減する効果も期待できる。 - デザインがシンプル
純正マフラーガードは、バイク全体のデザインに溶け込むように設計されているため、派手さはないものの、純正ならではの統一感がある。特に、オリジナルのデザインを大切にしたい人には、純正ガードが最適だ。 - 交換の手間が少ない
純正品は、もともとハンターカブに取り付けられているため、追加の加工や調整なしにそのまま使用できる。メンテナンス時の手間が少ないのもメリットといえる。
社外品のマフラーガードの特徴
一方で、社外品のマフラーガードには、純正品にはない個性的なデザインや機能性を備えたものが多数存在する。カスタムを楽しみたい人や、より高性能なガードを求める人にとっては、社外品の選択肢が魅力的だ。
- 多彩なデザインとカラー展開
社外品のマフラーガードは、ブラック塗装やクロムメッキ仕上げ、カーボン製など、純正にはないデザインやカラーが豊富に揃っている。特に、黒を基調としたカスタムを考えている場合、純正ガードよりもマッチするデザインが見つかる可能性が高い。 - 軽量で耐熱性に優れた素材
社外品には、アルミニウムやステンレス、カーボンファイバーを採用したものがあり、純正よりも軽量で耐熱性に優れているものが多い。軽量化を重視するライダーや、エンジンの熱によるダメージを抑えたい人には最適だ。 - カスタムパーツとの相性が良い
社外品のマフラーガードは、マフラー自体を交換するカスタムを施した場合でも、相性の良いものが見つかりやすい。例えば、「ヨシムラ製マフラー」を装着する場合、専用のヒートガードが用意されていることが多く、統一感を持たせることができる。 - 価格が幅広い
社外品のマフラーガードは、リーズナブルなものから高価なものまで幅広く、予算や求める性能に応じた選択が可能。ただし、安価なものは品質にばらつきがあるため、購入時にはレビューや評価を確認することが大切だ。 - 取り付けに工夫が必要な場合がある
純正品とは違い、社外品は必ずしもハンターカブにジャストフィットするわけではない。そのため、取付コンバーターブラケットキットを使用したり、微調整を行う必要がある場合がある。自分で取り付け作業を行う場合は、ある程度の工具や知識が必要だ。
どちらを選ぶべきか?
最終的に、純正マフラーガードと社外品のどちらを選ぶかは、ライダーのスタイルや目的による。
- 純正マフラーガードが向いている人
- そのままのハンターカブのデザインを維持したい
- 取り付けやメンテナンスを簡単にしたい
- 耐久性や安全性を最優先に考えたい
- 社外品マフラーガードが向いている人
- カスタムで個性を出したい
- 軽量で耐熱性の高いものを求めている
- マフラーを変更した際に適合するガードが欲しい
まとめ
純正マフラーガードは、メーカーが設計した安心感と取り付けの簡単さが魅力。一方で、社外品はデザインや素材の自由度が高く、個性を出したいライダーに適している。どちらも一長一短があるため、自分のバイクスタイルや用途に合わせて選ぶことが大切だ。
マフラーガードの材質と耐久性

ハンターカブのマフラーガードにはさまざまな材質が使われており、それぞれの特徴によって耐久性や使用感が異なる。選ぶ材質によって、見た目の印象だけでなく、熱への耐性や衝撃に対する強度、メンテナンスのしやすさが変わるため、用途や好みに合わせた選択が大切だ。
主なマフラーガードの材質と特徴
マフラーガードに使われる代表的な材質には、スチール、ステンレス、アルミ、カーボンファイバーの4種類がある。それぞれの特徴を詳しく見ていこう。
1. スチール製(鉄製)
スチールは、頑丈で耐久性が高く、コストパフォーマンスにも優れた素材だ。純正のマフラーガードにはスチールが使われることが多い。
- 耐久性:
衝撃に強く、転倒時のダメージをしっかり受け止めてくれる。特にオフロードや林道を走ることが多いライダーには安心の素材。 - 耐熱性:
高温に強く、マフラーの熱をしっかり遮断するため、安全性が高い。 - デメリット:
スチールは水分に弱く、塗装やメッキ加工を施していない場合は錆びやすい。そのため、屋外保管が多い場合や、雨の日の走行が多い場合は、定期的な防錆処理が必要になる。
2. ステンレス製
ステンレスはスチールに比べて錆びにくく、耐久性が高いのが特徴だ。社外品のマフラーガードでは、ステンレス製のものが多く販売されている。
- 耐久性:
スチールほどの衝撃吸収性はないが、強度は十分にある。転倒時にも比較的変形しにくい。 - 耐熱性:
スチールよりも熱を持ちにくく、マフラーの熱が伝わるのを防ぐ効果が高い。 - メンテナンス:
錆びにくいため、屋外保管でも比較的手入れが楽。ただし、表面が傷つくとそこから腐食が進むこともあるので、定期的なチェックは必要。
3. アルミ製
アルミは、軽量で扱いやすく、錆びにくいのが特徴の素材だ。カスタムパーツとして人気があり、多くのライダーが選択肢に入れる材質のひとつ。
- 耐久性:
衝撃にはやや弱く、強い力が加わると変形しやすい。特に転倒時に歪みが生じる可能性があるため、オフロード走行が多い場合は注意が必要。 - 耐熱性:
熱伝導率が高いため、マフラーの熱が直接伝わりやすい。ヒートガードの役割を果たすためには、適切な設計がされたものを選ぶ必要がある。 - デザイン性:
アルミは加工がしやすく、デザインのバリエーションが豊富。黒塗装やアルマイト加工が施されたものなど、スタイリッシュなカスタムパーツとしても人気がある。
4. カーボンファイバー製
カーボンファイバーは、近年人気が高まっている高性能素材。軽量かつ耐久性があり、スポーティなデザインが魅力だ。
- 耐久性:
衝撃には強いが、局所的に強い力が加わると割れやすい。転倒時に大きな衝撃を受けると、ヒビが入る可能性がある。 - 耐熱性:
非常に優れており、マフラーの熱をほとんど通さない。そのため、熱による影響を極力減らしたい場合には最適な素材といえる。 - デメリット:
他の素材に比べて価格が高い点がネック。また、カーボン特有の編み目デザインが好みでない場合には、選択肢から外れることもある。
耐久性と用途のバランスを考えた選び方

どの素材を選ぶかは、バイクの使用環境や求める性能によって変わる。
- 純正のままでも十分な場合:
メンテナンスの手間を減らしたい人や、普段の街乗りが中心のライダーは、スチール製の純正マフラーガードで十分な場合が多い。 - オフロード走行が多い場合:
転倒のリスクが高い環境では、強度のあるスチールやステンレス製が適している。耐衝撃性を重視するならスチール、錆びにくさを重視するならステンレスが選択肢に入る。 - カスタム性を重視する場合:
軽量化やデザインを重視するなら、アルミやカーボン製のマフラーガードが適している。特に、カーボンは軽量かつ耐熱性に優れるため、エンジンの熱対策にも効果的。
まとめ
マフラーガードの材質によって、耐久性や熱対策、見た目の印象が大きく変わる。スチールやステンレスは耐久性とコストパフォーマンスに優れ、アルミやカーボンは軽量でカスタム性が高い。それぞれの特徴を理解し、自分のバイクライフに最適なマフラーガードを選ぶことで、ハンターカブをより快適に楽しむことができるだろう。
「黒」塗装のマフラーガードのメリット

マフラーガードにはさまざまなデザインや素材があるが、中でも黒塗装のマフラーガードは多くのライダーに人気がある。単なる見た目の違いだけではなく、実用面でもメリットが多いため、純正品のまま使用するか、カスタムパーツに交換するかを迷っている人は、その利点を知っておくとよいだろう。
1. スタイリッシュな見た目
黒塗装のマフラーガードの最大のメリットは、引き締まったクールなデザインだ。ハンターカブはもともとアウトドアやアドベンチャー向けのデザインが特徴的だが、黒いマフラーガードを装着することで、より精悍で無骨な印象を与えることができる。
特に、フレームやエンジン周りをブラックで統一したカスタムをしている場合、純正のシルバーガードよりも黒塗装の方が全体のバランスが良くなる。純正のシルバーパーツが気になる人や、落ち着いたトーンでバイクを仕上げたい人にはピッタリの選択肢といえる。
2. 汚れや傷が目立ちにくい
オフロード走行やツーリングで頻繁に使用するハンターカブは、泥はねや小石の飛び散りによる傷がつきやすい。黒塗装のマフラーガードは、シルバーやクローム仕上げのものと比べて、こうした汚れや傷が目立ちにくいというメリットがある。
特に、純正のシルバーガードは傷がつくと光の反射で目立ちやすくなるが、黒塗装の場合は表面にマット加工が施されていることが多く、目立ちにくい。ツーリング中に多少の汚れがついても気になりにくいため、手入れの手間も軽減される。
3. 耐熱・防錆効果の向上
黒塗装されたマフラーガードの多くは、耐熱性や防錆性を向上させるために特殊なコーティングが施されている。例えば、耐熱塗装がされているものは、マフラーの高温による変色を防ぎ、長期間美しい状態を保つことができる。
また、塗装があることで表面の金属が直接湿気や水分に触れにくくなり、錆の発生を抑える効果も期待できる。特に雨の日の走行が多い人や、屋外でバイクを保管することが多い人にとっては、錆びにくい黒塗装のマフラーガードはメンテナンス面でも有利といえる。
4. カスタムの自由度が高い
黒塗装のマフラーガードは、純正のままでは得られないカスタムの自由度がある。例えば、ブラックのマフラーガードと相性の良いスリップオンマフラーを組み合わせることで、統一感のあるスタイルに仕上げることができる。
また、ブラックパーツとの組み合わせ次第で、シンプルなカスタムから、よりワイルドなオフロード仕様まで幅広いカスタムが可能だ。純正の雰囲気を大きく変えずに、さりげなく個性を出したい人には特におすすめのカスタムパーツといえる。
5. 夜間走行時の視認性向上
意外かもしれないが、黒塗装のマフラーガードには、夜間走行時の視認性を向上させる効果もある。純正のシルバーやクローム仕上げは、ヘッドライトの光を反射しやすいため、夜間に余計な光の反射が発生することがある。
黒塗装のガードは光の反射を抑えるため、ライダー自身の視界がクリアになりやすく、快適に走行できるというメリットがある。特に、林道や暗い山道を走ることが多い人にとっては、光の反射による視界の妨げを減らせる点は大きなメリットだ。
まとめ
黒塗装のマフラーガードは、スタイリッシュな見た目や汚れ・傷の目立ちにくさ、耐熱・防錆効果の向上など、多くのメリットを持っている。さらに、カスタムの自由度が高く、夜間走行時の視認性向上にも貢献するなど、単なる見た目の変更にとどまらない機能性の高さが魅力だ。
ハンターカブをより個性的に仕上げたい人や、メンテナンスの負担を減らしたい人にとって、黒塗装のマフラーガードは非常に有用な選択肢となる。自分のスタイルや使用環境に合わせて、最適なマフラーガードを選んでみよう。
ハンターカブのマフラーガードカスタム方法
- CT125 ヒートガードの純正仕様と交換方法
- ヒートガードの外し方と注意点
- CT125・CC110用マフラーガード取付コンバーターブラケットキットの活用
- ヨシムラ製マフラーガードの特徴と取り付け方法
- マフラーガードを黒に塗装する際のポイント
- Q&A
CT125 ヒートガードの純正仕様と交換方法

ハンターカブ CT125のヒートガードは、純正仕様でもしっかりとした機能を持っており、マフラーの熱からライダーを保護する重要なパーツだ。しかし、見た目のカスタムや追加の機能性を求めて交換を検討する人も多い。ここでは、純正ヒートガードの仕様と、交換方法について詳しく解説する。
1. CT125の純正ヒートガードの仕様と特徴
CT125の純正ヒートガードは、ホンダが設計した信頼性の高いパーツで、純正マフラーに最適な形状となっている。以下のような特徴がある。
- 耐熱性の高いスチール製 純正のヒートガードはスチール素材を採用しており、耐熱性に優れている。走行中に熱を分散させる構造となっており、ライダーがマフラーに誤って触れてしまった際の火傷を防ぐ。
- デザインの統一感 ハンターカブの無骨でアウトドア志向のデザインにマッチするシンプルな形状。マフラーと一体感のあるデザインになっており、後付けの違和感が少ない。
- 耐久性の高さ 純正ヒートガードは、転倒時の衝撃からマフラーを守る役割も果たす。オフロード走行などで万が一転倒した場合でも、マフラーが直接地面に接触するのを防ぎ、へこみや傷がつきにくい。
- メンテナンス性の良さ シンプルな構造のため、汚れがついても簡単に拭き取れる。サビ防止のための塗装が施されているが、長年の使用で劣化してくるため、定期的に確認しておくことが重要。
2. CT125のヒートガードを交換する理由
純正ヒートガードのままでも問題なく使用できるが、交換を検討する理由は以下のようなものがある。
- デザインを変更したい 純正のヒートガードはシンプルなデザインのため、より個性的なカスタムを求めるライダーにとっては物足りなく感じることがある。ブラック塗装のものや、メッシュデザインのものに交換することで、スタイルを強調できる。
- マフラーの放熱性を向上させたい 社外品のヒートガードの中には、純正よりも通気性の良い構造になっているものもある。これにより、熱がこもりにくくなり、特に夏場の走行時にエンジンのオーバーヒートを防ぐ効果が期待できる。
- 軽量化を図りたい 社外品にはアルミやカーボンファイバー製のものがあり、純正のスチール製よりも軽量なものが多い。少しでも車体を軽くしたい場合は、素材の軽さを重視したカスタムも選択肢の一つとなる。
3. CT125のヒートガード交換方法
ヒートガードの交換は比較的簡単な作業であり、特別な技術がなくても自分で交換できる。ここでは、交換手順を詳しく解説する。
準備するもの
- 新しいヒートガード(社外品または純正交換用)
- プラスドライバーまたは六角レンチ(取り付けボルトの種類により異なる)
- 軍手(熱くなったマフラーに触れないため)
- パーツクリーナー(取り付け前に汚れを拭き取る)
交換手順
- エンジンを冷ます マフラーは走行後に非常に高温になるため、交換作業を行う前に十分に冷ましておく。少なくとも1時間程度は放置しておくのが安全。
- ヒートガードの固定ボルトを外す ヒートガードは、マフラーのサイドに数本のボルトで固定されている。プラスドライバーまたは六角レンチを使って、ボルトを慎重に外す。ボルトを落とさないように注意。
- 純正ヒートガードを取り外す ボルトを外したら、ヒートガードをゆっくりと持ち上げるようにして取り外す。固く固定されている場合は、少しずつ力を入れて慎重に取り外そう。
- 新しいヒートガードを取り付ける 交換用のヒートガードを取り付け位置に合わせて、固定ボルトを仮止めする。このとき、すべてのボルトを一気に締めるのではなく、全体の位置を確認しながら均等に締めるのがポイント。
- ボルトをしっかり締める すべてのボルトを締めたら、緩みがないか確認する。ヒートガードがしっかり固定されていないと、走行中の振動で外れる可能性があるため、必ず最終確認を行う。
- エンジンをかけて確認 取り付け後、エンジンを始動し、異常がないか確認する。マフラーガードが適切に取り付けられているか、干渉して異音がしないかをチェックしておこう。
4. ヒートガード交換時の注意点
- 社外品は適合確認が必須 純正品とは違い、社外品のヒートガードは取り付けに加工が必要な場合がある。特に、海外製のパーツはネジ穴の位置が合わないことがあるため、購入前にしっかり適合確認を行うことが重要。
- 取り付けボルトはしっかり締める 緩んでいると、走行中に外れる可能性があるため、取り付け後は定期的にボルトの締まり具合をチェックする。
- 耐熱性のある塗装を選ぶ ヒートガードを黒塗装する場合は、必ず耐熱塗装を施されたものを選ぶ。普通の塗料では熱によって剥がれてしまうため、長期間使用するには耐熱性の高い塗料が必要になる。
まとめ
CT125の純正ヒートガードは耐久性とデザインのバランスが取れており、そのままでも十分な性能を発揮する。しかし、カスタム性や軽量化を求める場合は、社外品のヒートガードへの交換を検討するのも良い選択だ。
交換作業は比較的簡単で、自分でDIY作業として行うことも可能。適合確認をしっかり行い、安全性を考慮した上で、自分に合ったヒートガードを選ぶことで、より快適なハンターカブライフを楽しむことができるだろう。
ヒートガードの外し方と注意点

ハンターカブ CT125のヒートガードは、マフラーの熱からライダーを守る重要なパーツだ。しかし、メンテナンスやカスタムの目的で取り外すこともある。ヒートガードを外す際には、正しい手順で作業を進めることが重要だ。無理に取り外すと、ボルトやステーを傷めたり、再取り付けが難しくなることもある。ここでは、ヒートガードの正しい外し方と、作業時の注意点について詳しく解説する。
1. ヒートガードを外す前の準備
ヒートガードはマフラーに直接取り付けられており、走行後は非常に高温になる。そのため、作業前に準備をしっかり行い、安全に取り外せる環境を整えることが重要だ。
必要な工具
- プラスドライバーまたは六角レンチ(ボルトの種類により異なる)
- 軍手または耐熱グローブ(火傷防止のため)
- ラチェットレンチ(固く締まっているボルトを緩める際に便利)
- パーツクリーナー(取り外し前後の清掃用)
- ウエス(ボルトやパーツの汚れを拭き取るため)
作業前の注意点
- マフラーが完全に冷えているか確認する
走行直後のマフラーは非常に高温になっているため、最低でも1時間以上は冷やしてから作業を始める。熱いまま触れると火傷のリスクがある。 - バイクを安定した場所に停車させる
サイドスタンドやセンタースタンドを使用し、バイクが動かないようにする。特に、地面が不安定な場所では作業中にバイクが倒れる可能性があるので注意。 - ボルトの種類と位置を確認する
CT125のヒートガードは、マフラーの側面に複数のボルトで固定されている。作業前にどのボルトを外す必要があるかを確認しておくとスムーズに作業が進む。
2. ヒートガードの外し方
実際にヒートガードを外す手順を解説する。無理に力を入れて外そうとすると、ボルトが固着していた場合にネジ山を傷める可能性があるため、慎重に進めよう。
1. ボルトを緩める
ヒートガードは3~4本のボルトで固定されていることが多い。まずは、ボルトをすべて緩める。
このとき、すべてのボルトを一気に外すのではなく、均等に少しずつ緩めていくのがポイント。特に、固く締まっている場合は、無理に回すとネジ山をつぶす恐れがあるため、慎重に作業を進める。
2. 固着している場合の対処
長期間取り外していない場合、ボルトが固着していて簡単に外れないことがある。以下の方法を試してみよう。
- 潤滑スプレーを使用する
CRC 5-56などの潤滑スプレーをボルト部分に吹きかけ、数分待つことで固着が緩むことがある。 - ゴムハンマーで軽く叩く
ボルトやヒートガードを軽く叩いて振動を与えると、固着が緩んで回しやすくなる。ただし、強く叩きすぎるとパーツを傷めるので注意が必要。 - ラチェットレンチを使用する
一般的なドライバーで回らない場合、ラチェットレンチを使用するとより強いトルクがかけられるため、緩みやすくなる。
3. ヒートガードを取り外す
ボルトをすべて緩めたら、ヒートガードをゆっくりと取り外す。このとき、無理に引っ張るとステーやマフラー本体にダメージを与えてしまう可能性があるため、慎重に行おう。
ヒートガードが引っかかっている場合は、少しずつ角度を変えて調整しながら外すとスムーズに取り外せる。
3. ヒートガード取り外し時の注意点
ヒートガードを外す際には、以下のポイントに注意することで、スムーズかつ安全に作業が進められる。
- 取り外したボルトはなくさないように保管する
ボルトを紛失すると再取り付けができなくなるため、外したボルトはトレイや小袋に入れて管理する。 - マフラー本体に傷をつけないようにする
ヒートガードを無理に引っ張ると、マフラー本体に傷がつくことがある。特に社外品のマフラーに交換している場合は、塗装が剥がれやすいので注意が必要。 - 作業後に清掃する
ヒートガードを外した際に、マフラーに汚れやサビが付着している場合がある。取り外したついでに、パーツクリーナーやウエスを使って清掃しておくと、マフラーの寿命を延ばすことができる。 - 熱対策を考慮する
ヒートガードを取り外したまま走行すると、マフラーの熱が直接伝わり、火傷のリスクが高まる。新しいヒートガードを取り付けるまでの間は、なるべくマフラーに触れないように注意しよう。
まとめ
ハンターカブ CT125のヒートガードを外す作業は、それほど難しくないが、ボルトの固着やマフラー本体の傷つきを防ぐために、慎重に行うことが重要だ。特に、マフラーが十分に冷えていることを確認し、適切な工具を用意して作業することで、安全かつスムーズに取り外すことができる。
また、ヒートガードを外した後は、マフラーの清掃や、再取り付け時のメンテナンスを行うことで、長期間にわたって快適な状態を維持できる。カスタムやメンテナンスを楽しみながら、安全な作業を心がけよう。
CT125・CC110用マフラーガード取付コンバーターブラケットキットの活用

ハンターカブ(CT125)やクロスカブ(CC110)のカスタムでは、マフラーガードを交換したり、追加のガードを取り付けたりすることがある。しかし、純正マフラーとは異なるガードやカスタムパーツを装着する場合、取り付け位置が合わないことがあり、そのままでは取り付けできないケースも多い。そこで役立つのが「マフラーガード取付コンバーターブラケットキット」だ。このキットを活用することで、適合しないパーツでもスムーズに装着でき、より自由度の高いカスタムが可能になる。ここでは、コンバーターブラケットキットの特徴や活用方法、取り付け手順について詳しく解説する。
1. コンバーターブラケットキットとは?
マフラーガード取付コンバーターブラケットキットは、簡単に言うと「異なるタイプのマフラーガードを取り付けるためのアダプター」のような役割を果たすパーツだ。CT125やCC110には純正のマフラーガードが装備されているが、社外品のマフラーガードやヒートガードを取り付ける際に、純正のボルト穴や取り付け位置が合わないことがある。この問題を解決するのがコンバーターブラケットキットだ。
- 異なるメーカーのパーツを適合させる
社外品のマフラーガードや、他車種用のガードをCT125・CC110に取り付ける際、ボルト穴の位置が合わないことがある。このキットを使用すれば、適切な位置に固定できるようになる。 - 高さや角度の調整が可能
取り付け位置を微調整できるため、エンジンガードやサイドバッグとの干渉を避けつつ、見た目もスッキリと仕上げることができる。 - 強度と耐久性を向上
コンバーターブラケットを使用することで、マフラーガードの固定強度を増し、走行時の振動による緩みやズレを防ぐ。
2. どんなときに活用するべきか?
コンバーターブラケットキットは、以下のようなケースで特に活躍する。
- 社外品のマフラーガードを取り付けたいとき
純正のマフラーガードでは満足できず、別のメーカーのガードに交換したい場合に便利。 - ヒートガードや補助パーツを追加したいとき
純正のヒートガードだけでは不十分と感じる場合、追加のガードを取り付けることで、より広範囲をカバーできる。 - カスタムマフラーに交換した際にガードが合わないとき
社外マフラーに交換すると、純正のマフラーガードが取り付けできなくなることがある。このキットを活用すれば、適合しないガードも取り付けられるようになる。
3. 取り付け手順と注意点
必要な工具
- 六角レンチまたはプラスドライバー(ボルトの種類に応じて)
- ラチェットレンチ(締め付け強度をしっかり確保するため)
- 軍手(手を傷つけないため)
- パーツクリーナー(取り付け部の清掃用)
取り付け手順
- バイクを安定した場所に停める
作業中にバイクが動かないよう、センタースタンドまたはメンテナンススタンドを使用する。 - 既存のマフラーガードを取り外す
交換作業を行う場合は、まず純正のマフラーガードを取り外す。マフラーが熱くなっていると危険なので、事前に十分に冷ましておくこと。 - コンバーターブラケットを取り付ける
取り付け位置を確認しながら、ボルトを仮締めする。位置が適切かを確認した後、均等に締めていく。 - マフラーガードを取り付ける
コンバーターブラケットの取り付けが完了したら、マフラーガードを装着する。ボルトの締め付けは、対角線上に少しずつ行うと、しっかり固定できる。 - 締め付け確認と微調整
すべてのボルトを締めた後、マフラーガードがしっかり固定されているか確認する。また、走行時の振動で緩むことがあるため、取り付け後数日間は定期的に増し締めを行うとよい。
注意点
- ボルトの長さを確認する
取り付けるガードの厚みによっては、純正ボルトでは長さが足りない場合がある。必要に応じて適切な長さのボルトを用意する。 - 振動による緩みを防ぐ
走行時の振動でボルトが緩む可能性があるため、ネジロック剤を使用すると安心。 - 干渉チェックを行う
サイドバッグやエンジンガードとの干渉がないか、取り付け後に確認する。干渉がある場合は、取り付け位置を微調整するか、スペーサーを使用する。
4. おすすめのコンバーターブラケットキット

市販されているコンバーターブラケットキットには、さまざまな種類がある。以下のポイントを基準に選ぶと、満足のいくカスタムができる。
- 耐久性のある素材を選ぶ
アルミ製やステンレス製のものは、錆びにくく長期間使用できる。 - ボルトやスペーサーが付属しているものを選ぶ
取り付けに必要なボルトやスペーサーがセットになっているものを選ぶと、追加でパーツを買う手間が省ける。 - 調整幅があるタイプを選ぶ
角度や高さの調整が可能なものだと、細かいセッティングができるため、よりフィット感のあるカスタムができる。
まとめ
CT125・CC110用のマフラーガード取付コンバーターブラケットキットは、異なるメーカーのパーツを適合させるだけでなく、より自由度の高いカスタムを可能にする便利なアイテムだ。特に、社外品のマフラーガードを取り付けたい場合や、カスタムマフラーに交換した際にガードが合わないときには、大きな助けとなる。
取り付け作業自体は比較的簡単だが、ボルトの締め付けや干渉チェックをしっかり行うことで、より安全で快適なバイクライフを楽しむことができる。自分のカスタムスタイルに合ったブラケットキットを選び、ハンターカブやクロスカブをさらに魅力的な一台に仕上げよう。
ヨシムラ製マフラーガードの特徴と取り付け方法
ハンターカブ(CT125)をカスタムする際、マフラーのドレスアップや機能性向上のためにマフラーガードの交換を検討するライダーは多い。その中でも、ヨシムラ製のマフラーガードはデザイン性と実用性の両面で優れており、人気の高いアイテムだ。
ヨシムラは日本の老舗バイクパーツメーカーであり、高品質なエキゾーストパーツを提供している。そのヨシムラ製マフラーガードを取り付けることで、ハンターカブの外観を引き締めつつ、マフラーの保護やライダーの安全性を高めることができる。ここでは、ヨシムラ製マフラーガードの特徴と、実際の取り付け方法について詳しく解説する。
1. ヨシムラ製マフラーガードの特徴
ヨシムラのマフラーガードには、いくつかの明確な特徴がある。純正品と比較してどのような違いがあるのか、主なポイントを見ていこう。
① 高品質な素材と耐久性
ヨシムラ製マフラーガードは、耐久性に優れた素材を使用していることが特徴だ。一般的にはステンレス製やカーボン製が主流で、これらの素材は耐熱性に優れ、長期間使用しても変形しにくい。
- ステンレス製
頑丈で耐久性が高く、オフロード走行や転倒時のダメージを軽減できる。錆びにくいのも大きなメリット。 - カーボン製
軽量で熱を伝えにくく、マフラーの熱を効率的に遮断するため、ライダーの足を守る効果が高い。見た目にも高級感があり、カスタム性を重視するライダーに人気。
② エンジン熱からの保護性能
ヨシムラ製のマフラーガードは、マフラーの高温部分をカバーし、ライダーの足やズボンが直接触れることを防ぐ設計になっている。特に長時間のツーリングや渋滞時には、マフラーが高温になりやすいため、安全性の面でも大きなメリットがある。
③ デザイン性の向上
ヨシムラのマフラーガードは、無骨なハンターカブのデザインを引き締め、スポーティかつ洗練された印象を与える。ブラックやカーボン調の仕上げが施されたものが多く、純正よりもシャープな見た目になるため、カスタムの一環として取り入れやすい。
④ 軽量化によるハンドリング向上
カーボン製のマフラーガードを選ぶと、純正のスチール製よりも軽量になるため、車体の総重量を若干軽減できる。特に、軽量化を意識したカスタムを行っている場合、マフラー周りのパーツも見直すことで全体のバランスを調整できる。
2. ヨシムラ製マフラーガードの取り付け方法
ヨシムラ製のマフラーガードは、基本的に純正のマフラーガードと交換する形で取り付ける。専用の取り付けキットが付属していることが多く、比較的簡単に交換できるが、適切な工具を使用し、作業手順を守ることが大切だ。
必要な工具
- 六角レンチまたはプラスドライバー(ボルトの種類に応じて)
- ラチェットレンチ(しっかり固定するため)
- 軍手(手を保護するため)
- パーツクリーナー(マフラー表面の汚れを除去する)
- 耐熱グリス(取り付け部の摩擦軽減や防錆対策)
取り付け手順
① バイクを安定させる
作業をスムーズに行うため、センタースタンドまたはメンテナンススタンドを使用し、バイクが倒れないようにする。
② 純正マフラーガードを取り外す
純正のマフラーガードは数本のボルトで固定されている。プラスドライバーや六角レンチを使ってボルトを外し、慎重に取り外す。ボルトが固着している場合は、潤滑スプレーを使用すると緩めやすい。
③ ヨシムラ製マフラーガードの位置を確認する
取り付け前に、新しいマフラーガードの取り付け穴の位置が合っているか確認し、仮置きしてみる。
④ 仮締めして位置調整を行う
すぐに本締めせず、まずはボルトを軽く締める。全体の位置を確認しながら、ガードが適切な位置に収まるように微調整を行う。
⑤ 本締めして固定する
ボルトを均等に締めて、しっかり固定する。対角線上に締めることで、ガードが均等にフィットしやすくなる。
⑥ 取り付け後のチェック
取り付け後、マフラーガードがしっかり固定されているかを確認する。バイクを少し揺らしても動かないか、走行中に異音がしないかをチェックするとよい。
3. 取り付け時の注意点
- ボルトの緩みを定期的にチェックする
走行中の振動によって、ボルトが緩むことがあるため、取り付け後1週間程度は定期的に確認する。必要に応じて増し締めを行うことで、安全に使用できる。 - ヒートガードとの干渉に注意
社外品のヒートガードやエンジンガードと組み合わせる場合、干渉する可能性がある。取り付け前に適合確認を行い、必要ならスペーサーを使用する。 - 耐熱処理の確認
ヨシムラ製のマフラーガードは耐熱性に優れているが、取り付ける際に他のパーツと接触してしまうと熱がこもる可能性がある。適切な位置に取り付けることで、エンジン熱の影響を最小限に抑えられる。
まとめ
ヨシムラ製のマフラーガードは、デザイン性・耐久性・安全性を兼ね備えたカスタムパーツとして、多くのハンターカブライダーに支持されている。純正よりも高品質な素材を使用し、ライダーの安全を確保しながら、バイクのスタイルを向上させることができるのが大きな魅力だ。
取り付け方法も比較的シンプルで、自分で作業することも可能だが、確実な固定と干渉チェックを怠らないことが大切。カスタムの一環としてヨシムラ製のマフラーガードを導入し、より快適でスタイリッシュなハンターカブライフを楽しんでみよう。
マフラーガードを黒に塗装する際のポイント
ハンターカブのマフラーガードを黒に塗装することで、バイク全体のデザインを引き締めたり、無骨でスタイリッシュな雰囲気を演出したりすることができる。しかし、塗装の方法を間違えると、剥がれや色ムラが発生し、せっかくのカスタムが台無しになってしまうこともある。ここでは、マフラーガードを黒に塗装する際のポイントを詳しく解説する。
1. 黒塗装のメリット
マフラーガードを黒く塗装することで得られるメリットは多い。見た目の向上だけでなく、機能面でもメリットがあるため、事前に確認しておこう。
- スタイリッシュな見た目になる
黒塗装のマフラーガードは、ハンターカブのカスタムスタイルにマッチしやすい。特にブラックアウト仕様のカスタムを考えている人には最適だ。 - 汚れや傷が目立ちにくくなる
シルバーやクローム仕上げのマフラーガードは、小傷や汚れが目立ちやすい。一方で、黒塗装されたものは汚れが付きにくく、見た目のメンテナンスがしやすい。 - 耐熱・防錆効果が期待できる
適切な塗装を行えば、マフラーの熱に強くなり、錆びを防ぐ効果もある。特に、耐熱性のある塗料を使用することで、より長期間にわたり美しい状態を維持できる。
2. 塗装前の準備
マフラーガードを塗装する際は、下準備が非常に重要だ。適切な処理を行わないと、塗料がうまく定着せず、剥がれやムラの原因になる。
必要な道具
- 耐熱塗料(ブラック)
耐熱スプレー塗料を選ぶことが必須。マフラー周辺は非常に高温になるため、通常の塗料ではすぐに剥がれてしまう。 - ヤスリ(#400〜#800)
表面を整えて塗料の定着を良くするために、細かいヤスリを用意する。 - シリコンオフ(脱脂剤)
マフラーガードの表面の油分や汚れをしっかり落とすことで、塗料の密着度を上げる。 - 耐熱プライマー(下地塗料)
下地処理をしっかり行うことで、塗料の密着性が向上し、塗装の耐久性が高くなる。 - マスキングテープ・新聞紙
不要な部分に塗料がかからないようにするために必要。
塗装前の手順
- マフラーガードを取り外す
取り外さずに塗装すると、バイクの他の部分に塗料が付着するリスクがあるため、事前に外して作業を行う。 - 表面をヤスリがけする
表面を軽く削り、塗料が剥がれにくくなるようにする。古い塗装や汚れを落とし、滑らかな状態にすることが重要。 - 脱脂処理をする
シリコンオフなどの脱脂剤を使い、表面の油分を完全に取り除く。手の脂も付着しないよう、できるだけ手袋をして作業すると良い。
3. 塗装の工程
塗装は一度に厚塗りするのではなく、薄く何度も重ね塗りをするのが基本。焦らず丁寧に作業しよう。
塗装の手順
- プライマー(下地)を塗る
いきなり耐熱塗料を塗るのではなく、まずは下地として耐熱プライマーを塗る。これにより、塗料の密着が強くなり、剥がれにくくなる。 - 耐熱塗料を塗る(1回目)
スプレーは20〜30cmほど離して吹きかける。1回で厚く塗るのではなく、軽く吹きかける程度でOK。 - 乾燥させる(10〜15分)
1回目の塗装が終わったら、しっかり乾燥させる。完全に乾くまで待つことで、ムラや塗料の流れを防ぐことができる。 - 2回目・3回目の重ね塗り
2回目、3回目も同じように薄く塗り重ねていく。これを繰り返すことで、ムラなくキレイに仕上がる。 - 仕上げのクリア塗装(任意)
より艶を出したい場合や、耐久性を向上させたい場合は、仕上げに耐熱クリアを塗るのもアリ。 - 完全乾燥(24時間以上)
すぐに取り付けず、最低でも24時間は乾燥させる。しっかり乾燥させることで、剥がれにくくなる。
4. 塗装後の注意点
塗装が完了したら、長持ちさせるためにいくつかの注意点がある。
- 焼き付けを行う
耐熱塗料は、初めてエンジンをかけることで定着する。最初はエンジンを5分ほどかけ、その後冷ますという作業を2〜3回繰り返すと、塗料がより定着しやすくなる。 - こすらないように注意する
乾燥後すぐに強く擦ると、塗膜が剥がれやすくなるため、最初の数日は優しく扱う。 - メンテナンスを定期的に行う
小傷や剥がれが出た場合は、早めに補修することで美しい状態を保てる。
まとめ
マフラーガードを黒に塗装することで、ハンターカブの見た目が引き締まり、スタイリッシュな印象を与えることができる。しかし、適切な塗料や下地処理を行わないと、剥がれやムラの原因となるため、しっかりとした準備と丁寧な作業が必要だ。
耐熱塗料を使用し、薄く何度も重ね塗りをすることで、長持ちする仕上がりになる。さらに、焼き付け作業を行い、定期的にメンテナンスすることで、美しい状態を長期間維持できる。
ハンターカブのカスタムを楽しみながら、自分だけのスタイルを追求していこう。
関連する質問 Q&A

ハンターカブ(CT125)やクロスカブ(CC110)については、多くのライダーが気になる点がある。ここでは、よくある質問に対して詳しく回答する。これからハンターカブを購入する人や、既に乗っている人も、ぜひ参考にしてほしい。
Q, ハンターカブ 何キロ出る?
ハンターカブ(CT125)の最高速度は、おおよそ90km/h前後とされている。
ただし、これは平坦な道路での目安であり、ライダーの体重、風の抵抗、道路状況、エンジンのコンディションなどによって変動する。
- **ノーマル状態(純正仕様)**では、最大で90km/h程度が限界となることが多い。
- 社外マフラーやスプロケット変更を行うと、加速性能や最高速度を向上させることが可能だが、安全性とエンジンへの負荷を考慮する必要がある。
また、ハンターカブは最高速度を重視するバイクではなく、低回転からのトルクを活かした街乗りや林道ツーリング向けの設計となっているため、無理な高速走行はおすすめできない。
Q, ハンターカブは何キロまで走れますか?
ハンターカブは燃費性能が非常に優れているため、満タン時の航続距離はかなり長い。
- CT125(ハンターカブ)
- 燃費:約50〜60km/L(実燃費)
- 燃料タンク容量:5.3L
- 航続可能距離:約250〜300km(理論値)
- CC110(クロスカブ)
- 燃費:約55〜65km/L(実燃費)
- 燃料タンク容量:4.1L
- 航続可能距離:約230〜270km(理論値)
このため、ツーリングにおいてはガソリンスタンドの少ない山間部や離島でも、給油の回数を減らせるというメリットがある。ただし、積載量やエンジンの負荷によって燃費は変動するため、長距離を走る際は事前に燃料管理をしっかり行おう。
Q, ハンターカブは高速道路に乗れませんか?
ハンターカブ(CT125)は排気量125ccの原付二種に分類されるため、高速道路や自動車専用道路を走行することはできない。
- 125cc以下のバイクは、高速道路を走行不可
- 日本の法律では、125cc以下のバイク(原付・原付二種)は高速道路の走行が禁止されている。
- 自動車専用道路も走行不可
- 一部のバイパスや有料道路(例:首都高速、阪神高速など)も、高速道路と同様に125cc以下のバイクは進入できない。
例外として125cc以上のボアアップをした場合、高速走行が可能になることもあるが、車両登録を変更しなければならない(原付二種→軽二輪登録)。
このため、ツーリングを計画する際は、高速道路を使わずに走れるルートを事前に確認しておくことが重要だ。
Q, ハンターカブ110と125の違いは何ですか?
ハンターカブには、**CC110(クロスカブ110)とCT125(ハンターカブ125)**の2種類があり、それぞれの違いは大きく分けて以下の通り。
| 比較項目 | ハンターカブ CT125 | クロスカブ CC110 |
|---|---|---|
| 排気量 | 124cc | 109cc |
| エンジン | 空冷4スト単気筒(PGM-FI) | 空冷4スト単気筒(PGM-FI) |
| 最高出力 | 9.1PS/7,500rpm | 8.0PS/7,500rpm |
| 最大トルク | 1.1kgf・m/6,000rpm | 0.87kgf・m/5,500rpm |
| ミッション | 4速(リターン式) | 4速(ロータリー式) |
| 燃費 | 約50〜60km/L | 約55〜65km/L |
| 燃料タンク | 5.3L | 4.1L |
| 車両重量 | 118kg | 106kg |
| 足回り | フロントディスクブレーキ装備 | フロントはドラムブレーキ |
| サスペンション | フロント倒立フォーク | 一般的な正立フォーク |
| 価格 | 高め(40万円前後) | 比較的安い(35万円前後) |
① 排気量とエンジンの違い
- CT125(ハンターカブ)は124cc
排気量が大きいため、トルクが強く、オフロードやツーリング向き。 - CC110(クロスカブ)は109cc
低燃費で、街乗りや通勤・通学向きのバイクとして扱いやすい。
② ブレーキ性能
- ハンターカブ(CT125)はフロントディスクブレーキを採用
制動力が高く、急なブレーキングでもしっかりとした制動が可能。 - クロスカブ(CC110)はフロントドラムブレーキ
昔ながらの構造で整備性は良いが、制動力ではディスクブレーキに劣る。
③ サスペンションの違い
- CT125は倒立フォークを採用しているため、衝撃吸収性が高い。
悪路や未舗装路でも安定した走行が可能。 - CC110は一般的な正立フォークを採用し、コストを抑えつつも街乗りには十分な性能を持つ。
④ どちらを選ぶべきか?
- CT125(ハンターカブ)はツーリング・林道走行向け
→ 高い走破性と快適な乗り心地を求める人向き。 - CC110(クロスカブ)は日常の足や燃費を重視する人向け
→ コストパフォーマンスを優先するならこちらが適している。
ハンターカブ(CT125)とクロスカブ(CC110)は見た目が似ているものの、排気量や装備面で大きな違いがある。また、最高速度や航続距離、走行可能な道路などもライダーにとって気になるポイントだろう。
ハンターカブは最高速度こそ控えめだが、低燃費で長距離ツーリングにも適しており、125ccクラスの中でも特に人気の高いモデルだ。一方で、高速道路には乗れないため、ツーリングルートの計画を立てる際には注意が必要だ。
自分の用途に合ったバイクを選び、ハンターカブライフを存分に楽しもう!
まとめ:ハンターカブ マフラーガードの選び方とカスタムポイント
- ハンターカブのマフラーガードは熱からライダーを守る重要なパーツ
- 純正マフラーガードは耐久性が高く、標準の安全対策として優秀
- 社外品のマフラーガードはデザインや軽量化などカスタムの自由度が高い
- スチール製は耐久性に優れ、転倒時の衝撃を吸収しやすい
- ステンレス製は錆びにくく、メンテナンスが簡単
- カーボン製は軽量で耐熱性が高いが、衝撃に弱い
- 黒塗装のマフラーガードは傷や汚れが目立ちにくく、耐熱性も向上
- ヒートガードの交換でマフラーの保護範囲を広げられる
- ヒートガードの取り外しには適切な工具と冷却時間の確保が必要
- マフラーガード取付コンバーターブラケットで社外品も装着しやすくなる
- ヨシムラ製のマフラーガードはデザイン性と耐久性の両面で優秀
- 自分でマフラーガードを塗装する場合は耐熱塗料と下地処理が必須
- 125ccのハンターカブは高速道路を走行できないためルート選びが重要
- ハンターカブの燃費は優秀で、一回の給油で約250km以上走行可能
- クロスカブ110との違いは排気量やサスペンション、ブレーキ性能などにある